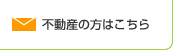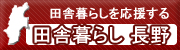印西の地域情報
海野作兵衛の頌徳碑
江戸時代に手賀沼の新田開発に尽力した海野屋作兵衛をたたえる石碑。発作地区にある「済民」と大きく刻まれた高さ3m程のもの。作兵衛は江戸・小田原町の諸大名に出入りする魚卸商人。幕府の方針により手賀沼に新しい水田を作ることになった折、彼が中心となって約229ヘクタールもの水田を作ったが、手賀沼の水害により堤防がこわされるなど被害にあったため、幕府から多額の借金をするとともに自分の財産を売り払い事業を継続したという伝承が残っている。彼の志は子、孫に受け継がれ、海野屋家が代々開拓事業に関わった160年の間に1290ヘクタールの新田を作り飢えに苦しむ農民を救った。この石碑は周辺10町村、約400人の農民の寄付によって建てられたもの。
曾谷ノ窪瓦窯跡
曾谷ノ窪瓦窯跡は、木下別所廃寺に使用された瓦を焼いた窯跡。7世紀の後半から8世紀の初頭のものと考えれられている。昭和54年に3基の窯跡が確認され、その内一つは発掘された。
白井市郷土資料館
白井市郷土資料館は、白井市文化センター内にある資料館だ。おもしろいのは常設展示ではなく市の郷土史がわかる資料などをテーマごとに数か月間づつけて展示しているとういうところ。
木下貝層(国指定天然記)
木下貝層は、約12?13万年前の地層。当時の関東平野は「古東京湾」と呼ばれる大きな海が広がっており、波や潮の流れによって貝類が集められ地層となったもの。木下貝層の名は、この貝化石類を多く含んだ地層が「木下」で最初に調査されたため。木下公園内で大きな露頭を見ることができる。
木下別所廃寺跡
木下別所廃寺跡は、8世紀初頭に建立されたもの。奈良の山田寺系の瓦が出土するのが特徴。発掘調査で3基の建物の基礎と畿内産の土器などが発見された。これはこの地域の交易の規模を示す貴重な資料となっている。